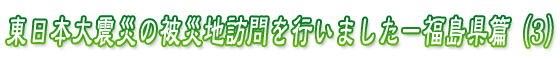
(第677回 9月26日 )
しばらくお休みしていましたが、被災地医療福祉生協訪問、福島県篇の第3回で、第669回(8月8日)の続きです。
9月15日から、帰還困難区域の特別通過交通制度の運用変更により、国道6号及び県道36号(小野富岡線)が通行できるようになりました(※参照)。私が訪問した時は、国道6号線は富岡町の途中(大熊町に入る手前)から、双葉町と南相馬市の境界付近までは、帰還困難区域に指定されており、一般車は通行禁止でした(関係市町村の通行証が必要)。しかし、この地域の空間線量はかなり高い地域もあり、復興はまだまだという感じです。
さて、7月13日に福島県の医療福祉生協の理事長、専務さんたちと懇談を行いました。参加したのは、福島医療生協(福島市)、郡山医療生協(郡山市)、浜通り医療生協(いわき市)、きらり健康生協(福島市。旧:福島中央市民生協)
復興の現状については、宅地の除染が進んできてはいるが、大幅に遅れている。宅地以外の山野の影響もあり、目標数値に届かないケースもある。仮置き場が決まらないため、除染で発生した汚染物質を宅地から持ち出せないため、線量の高い場所がありそれがストレスになっている。やはり、仮置き場の早期設置と、中間・最終処分場所についての合意形成が重要。
仮設、借り上げ住宅の居住者にとっては、プレハブの場合は、劣悪な住環境、家族や地域の分断など、人間関係の難しさや、運動不足からくる健康上の問題もある。また、心理的には、低線量の被ばくによる健康被害への心配が大きい。
など、深刻な現状が出されました。各法人の取り組みの紹介のあと、医療福祉生協連への期待としては、以下のような要望が出されました。
・サマーキャンプなど、こども保養の取り組みを続けてほしい。
・子供だけでなく大人の保養も必要。
・他県でリフレッシュする取り組みや、福島に来て、福島を知る、福島のものを食べる取り組みなども行ってほしい。
・現状の全国への広報
・情報の共有。マスコミは地元紙を除き、報道が殆どなくなっているため、福島県の地元紙(福島民友、福島民報など)の購読も検討してほしい。
・「脱原発」運動を全国に広げてほしい。
・放射線測定の重要性を高めるための支援活動。測定器の定期的校正、食品の非破壊式測定器の提供。
今後、可能なものから検討していく必要があります。
※国道6号等の通過(帰還困難区域の特別通過交通制度の運用変更)について
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/kokudou6gou.pdf
 |
|
 |
| 楢葉町の木戸川には鮭のやな場があったようです。いったん事故が起きたら、豊かな自然を一瞬にして「立ち入り禁止」区域にするの が「原発」の真の姿です。 |
|
緑色の シートの下には除染した草木や泥などがあります。仮置き場が決まるまではこのままの姿です。 |

|
|

|
| 津波が襲ってきた時間が克明に記録されています。 |
|
JR富岡駅前の慰霊碑です。 |
|
|